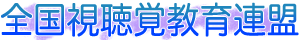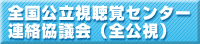私のことば/伝えようとする工夫
渡部 徹(国立教育政策研究所社会教育実践研究センター長)
私が青少年施設に勤務していた頃、研修会では8ミリや16ミリフィルムを上映したり、OHP等を利用していたが、機器の移動や設置、映写等で苦労したことを記憶している。
あれから35年以上過ぎて、映写機はパソコンや再生機器に、フィルムは電子媒体になり、資料の作成、編集、保存、移動、活用の方法などは格段に進歩し、利便性が向上するとともに資料内容や表現方法、教育手法も多様化している。
当センターは、社会教育指導者の研修等を実施しており、大学や行政関係、NPO法人等の多くの方々に講師をお願いしている。
講義は、ペーパーによる資料配付とパソコンの画面を併用した説明が多く見受けられ、文字やイラストはもとより、写真や動画、ホームページの画面等を活用するなどの様々な工夫が行われている。
行政や施設の職員など社会教育の経験が多様な受講者が参加する研修において、講師の方々には、社会教育に関する新たな知識や手法等について、受講者に理解してもらい、職場に帰ってからも活用できるよう、資料の作成や講義の仕方に工夫をして頂いている。講師の方々の講義に対する熱意や伝えようとする工夫、意欲が強く伝わってくる。
このような方々は社会教育指導者の養成に不可欠であり、当センター及び受講者にとっても大変にありがたいことである。講師の方々は当センターの大事な財産であると感じている。
最後に、国立教育政策研究所社会教育実践研究センターは、昭和40年に国立社会教育研修所として設置されて以来、平成27年で50周年を迎え7月に記念事業および式典を行いました。文部科学省生涯学習政策局の河村局長をはじめ、大学、教育委員会、社会教育団体の関係者や社研のOB・OGなど多くの方々のご参加を頂き、改めて、今まで支えて頂きました関係の皆様方に感謝を申しあげますとともともに、今後とも、社会教育を振興するための調査・研究の推進及び社会教育指導者の養成のために、ご支援を頂きますようよろしくお願い申しあげます。
平成27年度 第19回視聴覚教育総合全国大会/第66回放送教育研究会全国大会 合同大会報告

去る8月4日(火)・5日(水)の両日、第19回視聴覚教育総合全国大会並びに第66回放送教育研究会全国大会合同大会が、「ネットワーク社会におけるメディアとヒューマンコミュニケーション」をテーマに、東京都渋谷区・国立オリンピック記念青少年総合センターを会場に開催された。1日目午後からは各テーマごとに9つの実践発表を、中でも生涯学習ではパネルディスカッション「地域再生を目指したメディア利用の可能性と課題」をテーマに実施した。2日目午前は4つのワークショップ、2つの研究交流を実施、生涯学習では「地域映像の制作配信システムとその活用」をテーマに実施した。午後からは開会行事・功労者表彰式、NHKプレゼンテーション、大会のまとめ、スペシャルトーク(尾木直樹氏)などを内容とする全体会を実施した。2日間で延べ1、302名の参加を得て盛大に行われた本大会では、全国からさまざまな優れた実践はもちろん、今年度から新たな試みとして「アクティブ・ラーニングの実現に向けて」をテーマにタブレット端末を用いたワークショップを実施するなど、予想を上回る参加者を得て、実り多い大会となった。ここでは2日間の大会のもようを写真で紹介する。
●第1日目(8月4日(火))
【パネルディスカッション】

大会第1日目の全視連の生涯学習部会は、パネルディスカッション「地域再生を目指したメディア利用の可能性と課題」をテーマに実施した。
【加盟団体代表者会議・全国公立視聴覚センター連絡協議会総会を開催】

パネルディスカッションの後、標記会議および総会を実施。代表者会議では、行政説明として文部科学省生涯学習政策局情報教育課学習情報係長の高野智志氏による講演が行われた。その後、全国公立視聴覚センター連絡協議会総会が同会場において開催され、平成26年度事業経過報告書案及び平成27年度事業計画書案などが議事として提案され、異議なく承認された。
●第2日目(8月5日(水))
【研究交流(生涯学習)】

第2日目午前中は「地域映像の制作配信システムとその活用」をテーマとして研究交流が行われ、講師からの助言・指導を受け、会場からの積極的な質疑などもあり、実りある分科会となった。
【開会行事・功労者表彰】

午後の合同全体会は、最初に開会行事が行われ、主催者挨拶として視聴覚教育総合全国大会連絡協議会の会長として井上孝美氏が、また文部科学大臣祝辞として文部科学省生涯学習政策局長の河村潤子氏にご祝辞をいただいた。その他、各団体の功労者表彰式、NHKプレゼンテーション、大会のまとめ、スペシャルトークなどが実施された。
視聴覚教育功労者表彰 受賞者のことば

既報の通り、平成27年度の第18回全視連視聴覚教育功労者は、全国より13名の方々が選出され、去る8月5日、全国大会において表彰式が執り行われました。本欄では受賞者の方々の中から代表して岐阜県兼松氏、大阪府橋本氏、千葉県湯浅氏、鹿児島県野﨑氏により、受賞に際しての感想をいただきました。
「ボランティア活動に生きがいを求めて」
岐阜県 兼松賢三 氏

顧みますと、映写技術証を習得したのは昭和37年9月でした。当時、私は小学校に勤務していましたが、その時代は16ミリ映写が主流で、主に学校内や地域の映画会等の行事に携わってきました。平成元年に退職し、その後、市社会教育視聴覚協議会に入会し、現在に至っています。学校の週休二日制に対応し、毎月第4土曜日に実施する映画会、夏休みには親子「ファミリーシネマの夕べ」と題して、市内校下9会場で映画会を実施してきました。
さて、社会は各種情報機器の進歩により、高度・多様化し、そのニーーズに対応していかねばなりません。そのためには知識・技能を身につけていくことが大切です。私に残された人生も多くはありません。長い間お世話になったことに感謝し、少しでも社会に還元できることを願っています。平成23年に市社会福祉協議会が新しく「いきいきボランティア」という事業を立ち上げました。高齢者65歳以上の人達が活動を通じて、社会参加や地域に貢献しながらいつまでも元気で張り合いのある自立した生活を送れることを目的としています。現在、市には多くの老人福祉施設があります。私達の視聴覚協議会もこの事業に賛同し、施設からの要請に応じて映画会を実施しています。施設には様々な方が入所されており、内容の選定にはむずかしさはありますが、楽しんでいただける間は頑張っていきたいと思います。ボランティア活動は、子どもから高齢者までの幅広い世代にわたり、みんなの日常生活の中で、自分自身を自由に生き生きと表現する活動でもあると思います。仲間というつながりを大事にしながら、今自分のおかれている立場を考え活動していきたいと思います。
「視覚障害の方達の眼の代りを」
大阪府 橋本曠子 氏

この度は、大変名誉ある賞をいただき、永年の音訳ボランティア活動を支えてくれているグループの皆さんのお陰と感謝しています。私は幼い時から、声を出して本を読むのが好きで、ラジオの朗読の時間にはかじりつくようにして聴き、大人になったらこういう仕事をしたいと思っていました。念願叶って、成人してNHK大阪放送劇団に入り、毎日充実した日々でしたが、結婚と同時に退団、40歳を過ぎた頃、視覚障害の方のために、ボランティアで本を読むというのを知り、社会福祉法人日本ライトハウス盲人情報センターでボランティアとして本を読むことになりました。すべて家庭録音で、約十年間に、谷崎潤一郎の新々訳源氏物語(全巻)をはじめ、主として外国文学の名作(チボー家の人々、モーパッサンの女の一生、凱旋門、等々)六百余時間を録音、そのことで、昭和54年、日本盲人福祉協会より全国表彰をしていただきました。昭和55年、NHK文化センター(大阪)発足と同時に、ボランティア朗読講座の講師を引き受け、以来30余年、指導を続けています。十数年前、その卒業生の有志と共に、音訳グループ(N—BUN)を立ち上げ(現在会員98名)、毎月、月刊誌「オール読物=全頁約30時間」をはじめ、週刊新潮、おかずのクッキング、NHK短歌、ハイキング等、製作に追われる毎日です。朗読だけではなく、編集・発送その他より良く聴き易い音訳図書を届けるための日常のレッスンも欠かさず続けています。「今月の○○はよかった!」と利用者の方からいただくお電話が、私達の何よりの励みになっています。視覚障害の方の眼の代わりに、いろいろな情報を正確にお届けすることを忘れず、日々努力をしたいと思っています。幸、健康にめぐまれて、自分の好きな読むことに関わることの出来る喜びをかみしめながら。
「ビデオをやっていて良かった」
千葉県 湯浅純行 氏

今回、考えもしなかった名誉ある賞を戴く事になり感謝の気持ちでいっぱいです。
振り返ってみれば、平成元年に勤めていた会社を退職した後、機械ものが好きで動画が撮れると言うことだけで、持っていたビデオカメラを積極的にやってみる事にし、編集器、タイトラー、βのデッキ3台を購入しリニア編集を始めました。
アマチュアながらタイトルやBGMを入れられるのが楽しく、ビデオ撮影が目的で、花や素晴らしい風景を求めてよく出かける様になりました。撮影も的を絞って撮ったほうが良いと思い、野鳥撮影の勉強のため、千葉県野鳥の会に入会したのもこの頃で、シーズン毎に飛来する野鳥の名前を覚え撮影を繰り返し、実績を積み重ねるのも楽しみの一つでした。併し、当時のビデオカメラのファインダーはモノクロで動きの早い小鳥を探すのは大変で、プロの腕前の凄さを感じたものでした。
作品制作の勉強もしなくてはと思っていた矢先、ビデオ講習会が公民館であり、これに参加し勉強させて戴きましたが、これが私のビデオ人生の始まりになりました。
やたらにBGMを入れる私の作品をみて、音のない音と言うのもあるのだよと言われた鈴木幸雄先生(船橋市視聴覚センター)の提言は今でも鮮明に覚えています。この時作った作品を初めて千葉県メディアコンクールに出品したのが平成7年で、私の住んでいる町「我が町・北習志野」がNHK千葉放送局長賞を授賞し、以後平成27年まで20年間千葉に関する情報や行事などを、作品にしてきたのが、授賞の対象になったのかなと考えています。
この他にもボランティアで、市の行事の作品を作って寄贈したり、中学校のブラスバンドの活躍を作品にして差し上げたり、ビデオ制作は作る難しさや悩みは有りますが、作ったものが感謝されたり喜ばれると、ビデオ冥利に尽きると言うか、楽しいものです。
楽しみながら作っているのに、この様な素晴らしい賞を戴いていいのかなとも思っています。ビデオをやっていて良かった。
「隔世の感を覚える視聴覚教育」
鹿児島県 野﨑正寛 氏

この度は思いがけなくも、このような身に余る表彰を頂き、光栄に存じます。
私が視聴覚教育に携わったのは昭和46年、某ソフトクリームの専門メーカーに就職した時からです。この頃「ソフトクリームは大腸菌うようよ」と新聞紙上で騒がれていた頃で、業界としてはこの大腸菌との戦いがソフトクリームの売り上げに直結する緊急課題でした。この頃の食品衛生教育の教材と言えば、食品衛生法を省略した僅か一・二枚のコピーぐらいのものでしたが、私達は特に予算を計上して、原料の取り扱いから、フリーザーの洗浄殺菌等、衛生的なソフトクリームの作り方を解説した独自の映画を作りました。
そして全国各地で講習会を開きながらこの映画を上映、フリーザーの実技指導とともに本格的なソフトクリームの指導を始めました。その結果、全国のソフトクリームの衛生状態は目に見えて向上して行ったのは言うまでもありません。現場従業員の指導にとって、視聴覚教材の重要性をつくづく実感したものでした。
昭和57年、定年退職しましたが、これまでの経験から映像に興味を持っていた私は、丁度ビデオが民間に普及し始めた頃でもあり、迷わずビデオ機材を購入し、趣味としての映像制作を始めて今日に至っています。
近年は少子高齢化、それに過疎化の影響もあって、地域の郷土芸能などその伝承が危ぶまれています。
私はこのような文化財の記録と保存、伝承のためのツールとして、映像は最適のメディアではないかと確信し、現在、地域の伝統芸能や、民俗習慣行事等を取材し制作を続けています。そしてこの間、県の自作視聴覚教材コンクールにも参加しながらビデオ制作活動を楽しんでおります。
私が視聴覚教育に携わってすでに40数年、今回の授賞式に参加し、各ワークショップで垣間見た今日の視聴覚教育の環境に、隔世の感を覚えながら会場を後にしました。
第18回・平成27年度 全国視聴覚教育連盟視聴覚教育功労者 功績概要
| NO. |
都道府県名 |
功績概要 |
| 表彰者氏名 |
||
|
1
|
岩手県
菅原 桂子 |
「親子で映画を見る会」では若手映写技師として16年間に渡り優良映画の上映を続け、未来を担う子どもたちの健全育成に大きく貢献している。また、奥州市内で活動を続けている上映ボランティア集団「フィルマズ・アテルイ」では、子どもの日の映画上映会や地域の英雄を取り上げた長編アニメーション「アテルイ」を毎年上映するとともに、町内会の世代間交流会で 懐かしい16ミリ映画を上映するなど地区民にたいへん喜ばれている。それぞれの団体会員の高齢化が進む中で、若さと快活な行動力で地域住民に親しまれ、今後も更なる活躍が期待されている。 |
|
2
|
茨城県
高瀬 ヒロ子 |
平成元年4月から4年間大子町教育委員会社会教育指導員として視聴覚教育の発展に貢献する。平成15年4月から同24年3月まで10年間に及び読み聞かせボランティアグループ「森のおはなし会」代表として、地域の生涯学習の発展に尽力する。大子の民話を掘り起こし、18話の分かり易い紙芝居を作る。同22年10月には「大子の民話」という本を発行する。同26年6月から現在まで大子のラジオ放送FMだいごにて「読書のまち大子の民話」という番組の中で繰り返し同グループの朗読が放送されている。 |
|
3
|
群馬県
小和瀬 たかみ |
昭和58年の全国幼稚園放送教育大会「テレビ視聴を通し子どもの感性を育む」においての研究発表を機に、視聴覚教材の教育的価値に関心をもつ。以後、子どもたちにとって今必要なこと、経験させたいことを精選し、職員研修の一つとして学年毎に大型紙芝居、パネルシアター、絵ばなし、大型絵本などの教材開発に尽力。作品は群馬県自作視聴覚ソフトコンクールにおいて 平成8年を皮切りに、11年間にわたり最優秀賞、優秀賞等を獲得した。更に平成16年度全国自作視聴覚教材コンクールでは小学校部門(幼稚園も含む)で入賞。視聴覚教育の推進、幼稚園教育での活躍が認められ、平成27年度群馬県総合表彰を受賞した。 |
|
4
|
埼玉県
久木 健志 |
深谷市のIT戦略は全市的な取組みであり、情報教育メディアを学校に整備するだけでなく、教育センター並びに公民館、図書館等も充実している。そこで同人は同市教育委員会指導主事、副参事として学校教育だけの指導ではなく、同市立公民館や図書館、生涯学習センター等の社会教育現場でも視聴覚教材の活用を推進。市職員の電子データ化の研修の場として、また社会教育を担当する職員への研修会を企画・運営し、指導者養成も行った。特に、社会教育機関である図書館や生涯学習センター等の映像展示を推奨し、ビデオ映像やレーザーディスク映像の作成等を提案。社会教育における視聴覚教育の振興・発展に努力してきた。 |
|
5
|
千葉県
湯浅 純行 |
同人は、平成元年に民間企業を退職後、視聴覚機器を活用してビデオ制作を始め、平成7年の千葉県自作視聴覚教材コンクールにおいて特別賞・NHK千葉放送局長賞を受賞した。以後20年以上にわたり千葉県メディアコンクールに出品し、千葉県教育委員会教育長賞など数多くの賞を受賞している。同人のビデオ作品は千葉県の郷土を題材とし、最優秀賞・優秀賞を受賞した作品は学校教育、社会教育に有効活用されている。同人の地道な活動は、学校教育・社会教育における視聴覚教育の進展に大きく寄与し、他の範となっている。 |
|
6
|
神奈川県
後藤 基治 |
昭和53年7月に座間市視聴覚教育研究協議会に入会し、現在に至る。その間、地域の子ども会、自治会等で16ミリフィルムの上映を行い、視聴覚教育に貢献するとともに地区理事を2回つとめ、地域での活動を取りまとめた。座間市視聴覚教育研究協議会自主制作映画「おらがうまい水」では、制作委員会のメンバーとして自治会、市役所との調整役をつとめ映画の完成に活躍した。また、紙芝居の利用促進を図るなど新たな取り組みを行い、座間市視聴覚教育の振興に寄与している。 |
|
7
|
新潟県
石野 正彦 |
コンピュータの黎明期よりコンピュータを活用した授業に取り組み、実践的な研究を学会や雑誌等で数多く発表し、コンピュータを活用した授業の普及・進展に寄与した。昭和61年にJCOM(後の上越情報教育研究会)を創設し、精力的に活動を展開してきた。平成11年からは全国規模の情報教育研究会を毎年開催するとともに、平成22年にはJCOM会長として日本教育工学協会全国大会上越大会を開催した。上越地区広域視聴覚教育協議会の主催する高齢者パソコン教室に長年、講師として関わり続けているとともに、上越教育大学においても教職員自主セミナーを開催し、ICT教育に関するセミナーの講師として活躍中である。 |
|
8
|
岐阜県
兼松 賢三 |
平成6年4月、美濃加茂市社会教育視聴覚協議会加入。子ども会等での映画上映、同会主催の土曜映画会、ファミリーシネマなどの運営に中心的役割を果たす。また美濃加茂市社会福祉協議会主催の介護支援ボランティア事業に参加し、施設で映画会を実施するなど会の発展に貢献。同9年4月、岐阜地区社会教育視聴覚連絡協議会加入。同11年4月、美濃加茂市社会教育視聴覚協議会理事・上古井支部長就任。同12年10月、美濃加茂市社会教育視聴覚協議会長表彰受賞。同16年2月、岐阜県社会教育視聴覚協議会長表彰受賞。同21年2月、岐阜県教育委員会教育長表彰を受賞。 |
|
9
|
愛知県
丸山 英夫 |
長年にわたり、学校現場において視聴覚主任として、視聴覚機器・教材の整備に努め、授業においてその活用促進を図った。また、知多地方視聴覚ライブラリー協議会の運営委員として、自作視聴覚教材の制作や職員の指導に尽力する傍ら、全国自作視聴覚教材コンクールでは、2度にわたって文部科学大臣賞を受賞している。さらに、愛知県総合教育センター主催の視聴覚夏季講習会や東京の科学技術館で開催された講習会などでも講師を務めた。また、地域の博物館等から依頼された講座においても視聴覚教材を活用して、その普及や活用に努めるなど、同人は愛知県内だけでなく、全国の視聴覚教育の推進に寄与している。 |
|
10
|
大阪府
橋本 曠子 |
昭和56年4月、NHK文化センター(大阪、神戸教室)にて、ボランティア朗読講座の講師を務め、現在まで継続している。また、大阪府吹田市・堺市、兵庫県伊丹市・尼崎市・川西市のボランティアグループの指導・育成も、現在まで継続している。現在、音訳グル―プN-BUNを主宰し、会員90名と共に日本ライトハウス点字図書館を通じて毎月製作物(総合雑誌オール読物、週刊新潮等)をインターネット上のサピエ図書館に提出している。吹田市においては平成3年7月より永年にわたりボランティア養成講座の講師を続けている。 |
|
11
|
鹿児島県
野﨑 正寛 |
平成12年、さつま町郷土史研究会会員として郷土の文化芸能の保存・伝承活動のため映像制作活動を現在まで続けている。数多くの作品を自ら取材・制作し、平成12年度鹿児島県自作視聴覚教材コンクールでは最優秀賞を受賞、それ以降も入賞を重ね、平成25年度全国自作視聴覚教材コンクールでは文部科学大臣賞を受賞した。郷土芸能等を視聴覚教材にすることで、町民の郷土への関心を深め、広くは観光への貢献にも関わる。現在に至るまでさつま町の視聴覚教育の発展に大きく貢献するとともに文化振興にも尽力している。制作したビデオ資料65作品は教材として、町内すべての小中学校に配布され活用されている。 |
|
12
|
新潟市
雪松 眞美 |
新潟県立生涯学習推進センター「映画ボランティアの会」会員として、多年にわたり県民を対象とした毎月1回の映画鑑賞会を運営してきた。この3年間は映画ボランティアの会会長として、全会員の活動意欲を高め、県民にとって映画鑑賞がより深い学びの場となるよう、要求課題と必要課題のバランスを考慮した上映プログラム作りを推進してきた。通算上映回数は計180回を超え、多くの県民に優良な視聴覚教材に触れる機会を提供し、視聴覚教育の振興に大きく貢献した。 |
|
13
|
北九州市
田村 マサ子 |
昭和59年、知人の紹介で16ミリ映写機操作講習会を受講し、北九州市AVEの会門司区会に入会。以来、子ども会、幼児・児童施設、老人福祉施設、公共施設での巡回映写会を多い時には年間130回を超え開催。昭和63年からは、同会本部理事や門司区AVEの会会計の要職に就く。同会での31年にも渡る地道な活動と経験、リーダーシップを発揮し、北九州市視聴覚教育の普及や北九州市AVEの会会員の増強、操作技術の向上を目指している。何よりも映写会での参加者から寄せられる笑顔と感謝の言葉に、心からの喜びを感じながら、現在も活動を続けている。 |